|
|
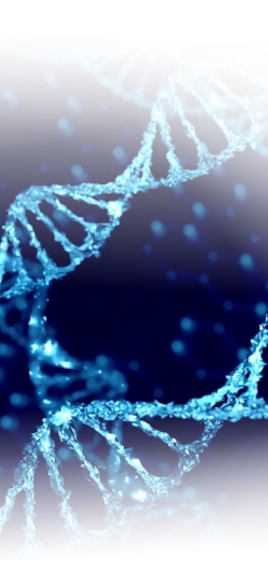
|
HOME > バックナンバー > 14/6月記事
アンチエイジングと長寿〜細胞のサビつきはカロリー摂取と相関
食べ過ぎは要介護になるというリスク
2013年6月4日(水)、東京都津田ホールで、平成26年度 第2回都民公開講座「アンチエイジングと長寿の秘訣」が開催された。講師に順天堂大学大学院加齢制御医学講座の白澤 卓二氏が招かれ、500人を超す来場者で会場は熱気に溢れた。
老ける人と老けない人の違いは「細胞の老化スピードの違い」
白澤氏は、「人は何歳まで生きられるのか?」という長寿や抗加齢の研究を続けている。
老けて見える人と見えない人との差は一体何にあるのか? 講演では、世界で最も長老のフランス人女性を紹介した。 彼女の名は、ジャンヌ・カルマン、122歳まで生きた。 カルマン氏は85歳からフェンシングを始め、100歳の時点でも自転車に乗っていた。フェンシングは、運動機能だけでなく、目や耳の機能が衰えていてはできない。カルマン氏は、おそらく80代でマイナス40歳くらいのアンチエイジングに成功していたのではないかと白澤氏はいう。 現在、日本で100歳以上の高齢者は5万人を超すといわれている。100歳以上になるとサクセスフルエイジングかアンサクセスフルエイジングのどちらかになるが、自立しているサクセスフルエイジングは18%で、残りの約80%は寝たきりというのが実情。 細胞のサビつきの促進にカロリーの摂取量が関わっている
サクセスフルエイジングを実現するための条件とは何か? 日本は食糧が豊かでない時代が長かったせいか、戦後は特にたくさん食べることを奨励するような食育を行ってきた。しかしながら、本来最も重要な食べ方とは「腹七分」でやめておくことであると白澤氏はいう。 また食事の内容では、栄養を補給しながらも低カロリーであることが重要で、赤毛ザルの実験で、栄養素を確保しつつ、カロリーだけを70%に制限した食事を17年間与えたところ、通常食のサルよりも髪の毛にツヤがあり、皮膚や運動能力が優れていたことが報告されている。 さらに、がんや脳卒中、心筋梗塞の発症もカロリー制限をしたサルのほうが少ないことも分かっている。つまり細胞のサビつきを促進させるのにカロリーが関わっており、食事を30%カロリーカットするだけで老化のスピードを遅らせることができると白澤氏。 その後の調査では、普通食のサルは全身の骨が骨粗鬆症になり、背骨も圧迫骨折し、ほとんど動けなくなってしまったという。 普通食のサルに前頭葉に萎縮 また、それぞれのサルの前頭葉をMRIで確認したところ、普通食のサルは前頭葉に萎縮が起こっていた。 人間も同様に、前頭葉は感情のコントロールを司る。ここが萎縮すると怒こりっぽくなったりする。また、同じ認知症でも前頭葉の萎縮が進んでいると、24時間監視が必要になったりするような、非常に厄介な認知症になるといわれている。 こうした栄養素を確保しながら、摂取カロリーだけを減らすという実験から分かることは、カロリー制限で老化や前頭葉の萎縮を遅らせられるということ。また、いくらカルシウムやビタミンを摂っていてもカロリーを多く摂っていれば十分な効果が得られないことを示している、と白澤氏。 食べ過ぎは要介護になるというリスク 団塊の世代の高齢化で、今後さらに高齢者人口が増加するが、赤毛ザルの実験からいえることは、「食べ過ぎ」は要介護に繋がる恐れがあるということ。そのために白澤氏は食事の摂り方で、まずよく噛むことを推奨する。 咀嚼は前頭葉と側頭葉のアンチエイジングトレーニングになる。そのため、20分以内で食事を終えている人はもっと咀嚼の回数を増やす必要があるという。 1口30回の咀嚼を心がけると、1食にかける時間は20分を超えることになる。これは1日60分のアンチエイジングトレーニングにもなる。実際に、サクセスフルエイジングの人は十分な咀嚼習慣があるという。 アメリカ産小麦のグルテンでアレルギーに また、アメリカでは品種改良が重ねられた小麦が普及しているが、この小麦はグルテンというタンパク質が大量に含まれており、昔の小麦とは全くの別物だという。 そのためパンもドーナツも驚くほどフワフワとした食感になっているが、グルテンは体内で完全に分解されないため、アレルギーの原因や脳に作用し麻薬のような中毒性を引き起こすといわれている。 実際に、アメリカではグルテンアレルギーの人が約100人に1人の割合で存在し、大問題となっている。こうしたアメリカ産小麦については注意が必要という。 その他、野菜ジュースを週3回以上飲んでいる人はそうでない人に比べ、76%もアルツハイマー病が少ない、なかでも手作りの野菜ジュースは食物繊維が豊富に摂れる、ことなども白澤氏は紹介した。 全身、特に脳の中にある幹細胞は年齢に関わらず、刺激で増える。そのため、生き甲斐のある、刺激のある生活で脳を刺激し続けることが大切とまとめた。
|
|
Copyright(C)GRAPHIC ARTS CO.,LTD. All rights reserved.
|